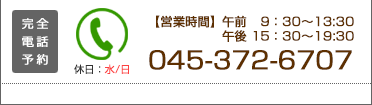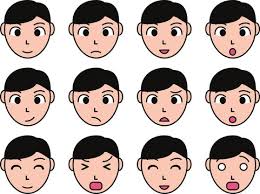操法する前と
操法した後とでは
顔の表情が緩むのが普通である。
顔の表情は、顔にある様々な
筋肉の緊張、弛緩のバランスで
作られている。
したがって、毎日違うし
瞬間、瞬間によって
変化するのです
操法することによって
顔の表情を作っている
筋肉が連動的に緩み、
その結果
顔の表情が緩むのです。
※解剖図を見ると、、、
顔の表情を作っている筋肉が
肩や、背中、腰などに
くっついている。
したがって、顔の筋肉を
じかにいじらなくても
変化することは明らかである。
だから、整体指導者は
その操法後の瞬間の
表情の変化を診て
緩んでいれば
(このまま、良い方向へと経過するだろう)
と感じ、
その日の操法を終えるのです。
反対に、こんなことが
あってはいけないが、、、
緊張が緩んでいなければ
・刺激の入れ方が多すぎたのか?
・ポイントがずれていたのか?
と、考え、、、
操法を初めから
やり直すこともあるのです。
追伸
ただ、体全体の筋肉を
まんべんなく緩めれば
「いい」と、言うことではなく
自力で緩めることが
できなくなっている
箇所の筋肉を見つけ出し
それを調整する事が
重要になってくるのです。
※全身の筋肉を緩めすぎると
顔の表情が「呆けた」ように
見えることもある。
緩めすぎた、と言うことなのです。
関連記事
- 2020.12.17
お腹の力が抜けた時の人体力学体操の要点 - 2020.08.17
熱中症の兆し(ふくらはぎがつった) - 2020.06.15
買い物の荷物を重く感じる - 2020.06.03
枝を切っただけでぎっくり腰 - 2020.09.20
朝までエアコン - 2020.08.12
「ため息」を付くことによってストレスから体を守る
![-井本整体横浜室-よしみ整体[鈴木好美]](/wp-content/themes/yoshimi-seitai/images/logo.png)